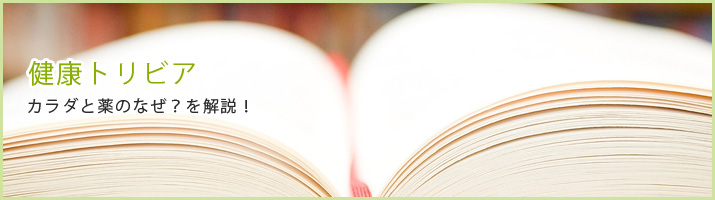
内臓が元気でないと体にハリがでません。内臓には食物を消化・吸収してエネルギーに換える胃腸や肝臓があり、体の老廃物を排出する腎臓、膀胱や大腸もあって、それらの働きは主に自律神経によって調節されています。
また、内臓は脳と密な連携をしているので、体だけでなく、心の健康にも関係しています。
★☆内臓の働きはいろいろとある ☆★
消化管(特に胃腸)は、食物の消化・吸収、排泄に関係しています。その役割を果たすために、胃腸の粘膜層に自律神経や知覚神経終末が配置されています。さらに胃腸を取り囲んでいる筋層には独自の神経ネットワークが構成されていて、胃腸全般の働きがコントロールされています。
腸管(主に大腸)には、100兆個もの腸内細菌が棲息しており、その腸内細菌フローラは腸管の分泌能や代謝能、さらに、粘膜層で細菌などの微生物排除に働いている腸管免疫の成熟や機能維持にも影響を及ぼしています。
腸内細菌フローラを構成する腸内細菌はビタミンB群やビタミンCを合成してくれますので、お腹を壊すとビタミン不足になってイライラしたりすることもあると、言われています。
★☆内臓がうまく働かなくなると、どうなる?☆★
①代謝
内臓は栄養分の取り込みという重要な働きをしているので、その機能が弱ると、エネルギー産生が低下し、代謝他全ての機能が低下して、疲れや胃腸障害、生活習慣病にもつながります。また、老廃物の排出や異物の除去にも支障が生じます。
②腸管免疫
腸管には全身の免疫の6~7割を担っている免疫組織があります。その腸管免疫の免疫細胞は、共存する腸内細菌が産生する刺激物質によってその機能が維持・調節されています。ストレスなどで腸内細菌のバランスが乱れると、免疫反応の調節の仕組みに狂いが生じて、いろいろな不快な症状が発生すると言われています。
③脳-消化管
内臓はストレスを映す鏡と言われる様に、不安や緊張を感じるとすぐに内臓は不調を訴えます。ストレスによって腸内細菌のバランスが崩れると、腸内細菌が病原性を出現させたり、脳に異常な刺激が伝わったりして、体や心にも悪影響を及ぼしてしまいます。職場でのストレスや、年末年始の暴飲・暴食などが続くと腸内細菌のバランスを乱す原因になります。また内臓が弱ると、気分が落ち込んだり、イライラしやすくなります。
最近、腸内細菌が脳内で働く物質を造り、脳のはたらきに関与しているという仮説があり、その可能性が議論されています(下図参照)。 腸内細菌のバランスの乱れが原因と考えられるうつ病など精神疾患の改善に関しては、今後の研究成果が待たれます。
★☆内臓を元気にするには?☆★
脂肪やタンパク質が多く野菜の少ない食事、ストレスや便秘・下痢、加齢は腸内細菌のバランスを乱し、腸管免疫が低下する要因となります。ストレスをためず、バランスのよい食事をとり、適度な運動や良好な排便をこころがけることで、腸内細菌のバランスを整えましょう。腸を元気にするためにやりたいこと、摂りたいものを以下紹介いたします。
①適度な運動
腸の蠕動運動の停滞を回復し、便秘の解消に効果的です。又、糖や脂質の代謝異常を改善し、腸内環境の向上につながります。
②乳酸菌
糖分を分解し、乳酸や酢酸を産生して腸内環境を弱酸性にすることで、悪玉菌が増加するのを防ぎます。また、乳酸菌の一種であるビフィズス菌には、有害物質の侵入を防ぐ抗体産生を増強する働きがあります。また、乳酸菌を摂ると免疫バランスが整い、アレルギーになりにくくなると言われています。
③食物繊維、オリゴ糖
これらは腸管で消化・吸収されにくく、大腸まで届くと乳酸菌などの善玉菌のエサとなって、増殖を助けます。
【営業時間】
9:00~19:00
木曜・土曜 9:00~18:00
TEL:0466-22-8609
【営業時間】
9:00~18:30(12:30~14:30は休)
土曜 9:00~13:00
TEL:0466-29-5030