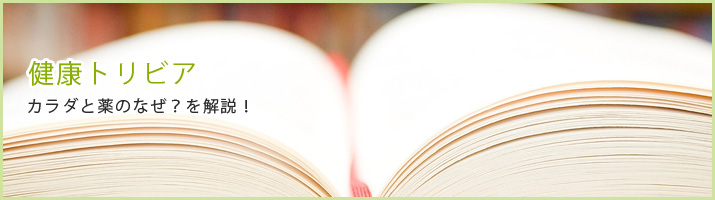
ミネラル(無機質)とは、地球上に存在する元素のうち、水素、炭素、窒素、酸素を除いたものです。必要な量は少ないですが、体の中では作ることができないので、食べ物からとる必要があります。ミネラルは、骨などの体の組織を構成したり、体の調子を整えたりする働きがあります。そのようなミネラルの大切さをご紹介いたします。
◆ミネラルの体内での働き◆ :大部分は骨や歯に存在し、体のバランスを保つ!
ミネラル (mineral)という名前は、mine (鉱山・鉱石など)や金属を意味するmetalという言葉に由来しています。それぞれの名前は発見された場所の地名やギリシャ神話、その金属を含んだ物質の色など様々な由来から名付けられています。ミネラルの役割は大きく4つあります。
①骨・歯・血液など体の構成成分になる
②神経・筋肉機能を正常に保つ
③酵素の働きをサポートする
④体液の浸透圧・pHを調整する
ミネラルの80%以上は骨や歯にあり、リン酸カルシウム、リン酸マグネシウムとして存在し、強さ、 硬さ、弾力、耐性を与えています。約10%はタンパク質などと結合して筋肉内にあり、約1%は細胞膜や酵素などの材料として存在しています。
◆不足しやすいミネラル・摂り過ぎるミネラル◆ :ミネラルはバランスよく摂ることが大切!
【不足しやすいミネラル】
●カルシウム(摂取基準:男女 650 mg)
日本人に長年不足しているミネラルです。また、生体内で最も多く存在するミネラルで、骨や歯、血液、筋肉に存在します。年齢によって吸収量が変化するので、カルシウムの摂り方を工夫してみましょう。
●亜鉛(摂取基準:男 10 mg、女 8 mg)
多くの酵素に含まれ、遺伝子発現、たんぱく質合成など、細胞や髪の成長と分化に中心的役割を果たしています。不足により、味覚障害や皮膚炎、食欲不振などが起こることが知られています。亜鉛(摂取基準:男 10 mg、女 8 mg)
多くの酵素に含まれ、遺伝子発現、たんぱく質合成など、細胞や髪の成長と分化に中心的役割を果たしています。不足により、味覚障害や皮膚炎、食欲不振などが起こることが知られています。
●マグネシウム(摂取基準:男 370 mg、女 290 mg)
古代ギリシアのマグネシアという地域で採れたことからマグネシウムと名付けられました。マグネシウムは、ほとんど全ての生合成反応や代謝反応に必須のミネラルです。また、カルシウムと密接に関与し、骨の健康を維持する働きもあります。
【摂り過ぎが心配なミネラル】
●ナトリウム(摂取基準:食塩として男女 7 g未満)
神経伝達や筋収縮などに関与している重要なミネラル。しかし、摂りすぎると高血圧や脳卒中など、生活習慣病に繋がります。摂取基準量を目標に食事を工夫しましょう。
《カルシウムバランスの 重要性》
カルシウムは「生命の炎」と言われ、血液中のカルシウム濃度が一定に保たれているために心臓や脳、その他の器官が正常に働き、人間の生命を保っています。
カルシウム摂取量が不足すると、副甲状腺ホルモンが分泌され、骨からカルシウムを取り出し、血液中の濃度を一定に保とうとします。慢性的にカルシウムが不足していると、常にカルシウムが骨から溶かし出され、骨粗鬆症に繋がります。また、骨から過剰にカルシウムが溶かし出されることで、動脈硬化や脳梗塞、結石などの病気に繋がります。
◆ミネラルの種類と多く含む食品◆ :健康管理は食事が基本!
ミネラルは様々な食品に入っています。バランスよく摂りましょう!
出典:「井上正子監修 新しい栄養学と食のきほん事典 西東社」 「農林水産省 ミネラルとは」
「中村丁子監修 栄養の基本がわかる図解事典 成美堂出版」 「食品と開発 Vol. 49 No. 5」
【営業時間】
9:00~19:00
木曜・土曜 9:00~18:00
TEL:0466-22-8609
【営業時間】
9:00~18:30(12:30~14:30は休)
土曜 9:00~13:00
TEL:0466-29-5030