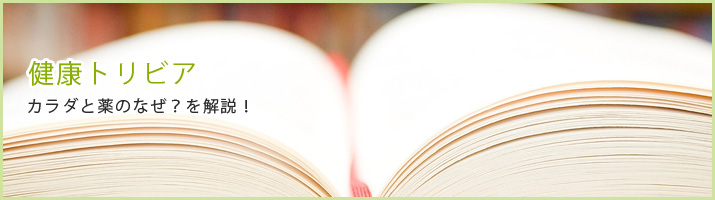
私達の腸内はおよそ数百種類、100兆個もの腸内細菌が共存している特殊な空間です。敷き詰められた腸内細菌はお花畑=“フローラ”と例えられる事があり、近年、私達の身体にとって有益な働きがある事が次々と解明されてきています。
▼腸内フローラ▼
一般的に、腸内細菌は善玉菌、日和見菌、悪玉菌に大きく分けられます。善玉菌は、乳酸や酢酸などの有機酸を産生することで腸内を酸性に保ち、酸に弱い病原性細菌の増殖を抑える事で、良好な腸内フローラ(腸内細菌叢)を形成しています。
私達の食生活の乱れは、腸内フローラにも大いに影響します。そして、腸内フローラの住む腸管へも影響します。近年、腸管上皮組織のバリア機能の低下(すき間)が確認され、そこから様々な物質が血液中に移行する事で、多岐にわたる病気の原因になってしまう事がわかってきました。同時に、腸内フローラが良好な状態であれば、善玉菌がこのすき間を修復してくれるという事も確認されました。なかなか症状が改善されなかったり、原因の特定できない不調が続く背景には腸内環境の悪化が原因にあるかもしれません。
まずは、腸内フローラの乱れがどのような症状と関連性があるか確認していきましょう。
腸内フローラが乱れると・・
糖尿病!?メタボ!?
食生活の乱れはメタボの主な原因です。特に、脂肪の多い食事は腸内フローラを乱してしまいます。バリア損傷部位(すき間)を悪玉菌やそれらが産生する物質が通過し、その先で炎症を引き起こします。炎症物質はインスリンの効きが悪くなるインスリン抵抗性の原因となる事もわかってきました。
腸内フローラが乱れると・・
アレルギー!?
食事や病原体由来の未消化タンパク質などがバリア損傷部位(すき間)から多量に流入する可能性があります。正常なルートからの侵入ではないために、身体が異常に反応してしまい、アレルギー(IgE抗体産生)や自己免疫疾患の発症に関わると考えられています。
腸内フローラが乱れると・・
イライラ!?ストレス!?
ヒトの腸には大脳に匹敵するほどの細かな神経細胞が張り巡らされています。そのため、脳の指令なしに働く事が出来るのが腸であり、最近では「腸脳相関」と呼ばれる双方向のネットワークを形成している事がわかってきました。腸内フローラの状態が精神にも影響する可能性が示唆されています。
▼腸内フローラのために▼
私達は、腸内細菌が上皮のバリア損傷部位(すき間)を修復する働き以外にも、発酵過程で腸内細菌が生み出す短鎖脂肪酸による恩恵を受けています。酢酸、プロピオン酸、酪酸などの短鎖脂肪酸は上皮細胞の栄養素となり大腸の蠕動運動を活性化したり、腐敗菌や有害物質の産生を抑える働きが確認されています。また、血液中に移行した後、脂質代謝にも関与し身体にとって良い働きを示す事が明らかになっています。腸内環境の悪化には、食事、ストレス、加齢、便秘・下痢、抗生物質の長期使用などの影響が考えられています。腸内フローラが良好な状態に保つための生活習慣について、改めて考えてみてはいかがでしょうか。
【腸内フローラを育む!】
乳酸菌などの善玉菌の摂取も大切ですが、それと共に食物繊維・オリゴ糖などの今現在私達の腸内に存在している菌を育むための食材をバランス良く摂取する事も大切です。ヒトはこれらの食材を消化・吸収する事はできませんが、善玉菌にとっては大切な栄養源となります。腸内フローラを育むために、日頃の食生活で以下のような食材を摂取できているか確認してみましょう。
□バナナ、□リンゴ、□干しぶどう、□抹茶、□ハチミツ、□大豆、□豆乳、□枝豆、□さつまいも、□玄米、□かぼちゃ、□ごぼう、□しいたけ、□ひじき、□アーモンド、□くるみ、□山いも、など
参考;菌活のはじめ方/辨野義己
【営業時間】
9:00~19:00
木曜・土曜 9:00~18:00
TEL:0466-22-8609
【営業時間】
9:00~18:30(12:30~14:30は休)
土曜 9:00~13:00
TEL:0466-29-5030