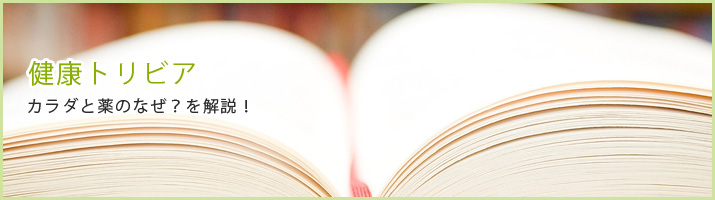
従来、骨の健康のためには骨塩量が大切ということで、カルシウムなどのミネラルを積極的に摂取することがすすめられてきました。ところが慈恵医大の調査で、骨粗鬆症で薬物治療を行っているにも関わらず、骨折を予防できないケースは約半数に昇るということが分かりました(50%の壁)。そのため近年は、骨の強度を保つために、骨塩量とともに骨の質(骨質)にも注目されるようになってきています。寝たきりにつながる恐れのある骨粗鬆症予防のため、今回は骨の強度と骨質という観点から、骨の強度を科学的に見て行きましょう。
▼骨の中身は?
骨はミネラルとコラーゲンでできており、鉄筋コンクリートに例えると、ミネラルがコンクリート、コラーゲンが鉄筋に当たります。骨のミネラルは、そのほとんどがカルシウムとリンです。骨の強さは、以前は骨密度(カルシウム濃度)が重要と言われてきましたが、近年は鉄筋の役割をしている骨質(コラーゲン分子とコラーゲン分子同士をつなげる架橋)の大切さが注目されています。
▼骨質が悪いと、どうなる?
鉄筋にあたるコラーゲン分子同士は、「架橋」によりつなぎとめられています。秩序正しく分子をつなぎとめる「善玉架橋」は、骨に柔軟性を生み出し、外からの刺激をある程度受け止めることに貢献します。ところが、無秩序・不正に分子をつなぎとめる「悪玉架橋」は、骨をチョーク(白墨)のようにもろくして、外からの衝撃を受ける力を弱くし、骨折につながることがあります。骨の強度の30%は骨質によると言われており、骨密度が低い※ことに加えて、悪玉架橋が多く骨質が低下している方は、正常な方に比べて7.2倍も骨折しやすいと言われています。
※健康な骨の指標である骨密度平均値は、70~80%
▼骨質を悪くするものは?
島根大学の疫学調査や各種報告から、動脈硬化、高血圧や糖尿病といった生活習慣病を患っている方や心筋梗塞、脳卒中の経験者は、骨密度が高くても骨折しやすいことが分っています。このような報告から、骨質を悪くする原因として、以下の2種類が指摘されています
①ホモシステインの増加
ホモシステインは、タンパク質を構成するアミノ酸のメチオニンが代謝されてできる硫黄化合物で、活性酸素を発生し、悪玉架橋を増やすと言われています。またビタミンB6、B12や葉酸が不足していると、ホモシステインが増えやすいとされています。
②最終糖化反応生成物(AGEs:Advanced Glycation Endproducts)、糖化タンパクの蓄積
体内の活性酸素量が増えたり、血糖値の高い状態が続くと、骨のコラーゲンに「最終糖化反応生成物(AGEs)」や糖化タンパクが、悪玉架橋として蓄積します。
【参考:日経サイエンス2010年10月号】
▼骨の健康のために心がけることは?
骨質に注目して骨折のリスクを下げるために、以下の3点を心がけましょう。
(1) 生活習慣病を予防する
悪玉架橋を増やさないため、血管の病気や糖尿病といった生活習慣病の予防に努めましょう。特にホモシステインを増やす『ビタミンB6の不足』や、糖化タンパクを増やす『糖分のとり過ぎ』に注意しましょう。
(2)内臓を元気にする
内臓を元気にすることで、ホモシステインや、最終糖化反応生成物の代謝を促すことが期待できます。特に代謝に関わる肝臓、排泄に関わる腎臓を元気にすることを心がけましょう。
(3)適度な運動を心がける
適度な運動は骨に刺激を与え、カルシウムが骨に沈着するのを手伝います。ただし無理をして転倒などのケガにつながらないようにしましょう。
【営業時間】
9:00~19:00
木曜・土曜 9:00~18:00
TEL:0466-22-8609
【営業時間】
9:00~18:30(12:30~14:30は休)
土曜 9:00~13:00
TEL:0466-29-5030